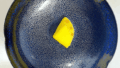仏芋(つくねいも)と上白糖を丁寧に混ぜあわせ、上用粉を練り込んで仕立てた生地で「こし餡」を包み込み、いろどりを添えて蒸し上げたお饅頭。
ひと口ふくめば、薄皮のもっちりとした歯ざわりのあとに、こし餡の風味がふわりと広がり、やさしい甘さが静かにほどけてゆきます。お茶席にふさわしい、上品な和菓子のひとつです。
上用(じょうよう)饅頭は、薯蕷(じょうよ)饅頭とも書きます。 漢和辞典によれば、「薯」とは、芋のこと。解字をみれば、署には、集まる・中身が充実するという意味があり、+草かんで根が充実して太い芋という意味を表すようです。
そして、「蕷」の方も芋のこと。同じく漢和辞典の解字によれば、預は、予と同源。そして予とは、横に伸びるイメージです。横に伸びるとは、芋のつるや、地下に張る根を連想させます。つまり芋のつるや根の特徴をとらえた漢字と言えそうです。
また、預という字に含まれる「頁」は、「頭」という意味を持たせるときの限定符号とのことですが、今回は無視で良いと思います。これに+草かんなので、蔓性の芋の意となります。
つまり、薯も蕷も芋を表します。それゆえに「薯蕷」とは、芋の力強い生命力を感じさせる言葉と言えそうです。
「薯蕷饅頭」とは、一見繊細な表記でありながら、実は「芋饅頭」を意味します。 それゆえなのかもしれませんが、「上用饅頭」という表現で上品な和菓子を表しているのかもしれませんね。
ただ、「上用」という表現にも、やや簡略な印象が伴います。
そこにおいて、お饅頭自体に緑の色彩を加え、幾つかの焼き印を施したものを「織部(おりべ)饅頭」と称します。
上用饅頭そのものを武将・茶人 古田織部にちなんだ陶器になぞらえて、「織部」と呼ぶのです。
これこそまさに和菓子を器になぞらえて、物の見方さえも変えて愉しむという、お茶のたしなみの世界観と言えるのかもしれませんね。